「社会デザイン・フューチャーセッション」授業レポート

2018年から開講し、今年で2年目となる「社会デザイン・フューチャーセッション」。これから社会に出て仕事に携わる学生にとって、将来のキャリアデザインを考えるヒントが詰まった授業です。
建築に関わる仕事の中で、面白い働き方や活動をしている人たちは、都市や社会をどのようにデザインしているのでしょうか? 今年は2日間の開催で計5名のゲストを招き、仕事に取り組むうえでの考え方や目指すもの、これまでのキャリアをどのように築いてきたかなど、リアルなお話を聞きました。その様子をレポートします。
「社会デザイン・フューチャーセッション」での学び
大学を卒業・修了したあと、建築に関わりながらどのように都市や社会をデザインしていくか? これからのキャリアを考えながらキャンパスライフを送る学生にとって、建築の現場で働く先輩たちのリアルな話が聞けるのは貴重な機会です。「社会デザイン・フューチャーセッション」では、第一線で働く人をゲストに招き、対話によって学生たちの能動的な思考を引き出します。本年度の講義の全体調整を担当したイスラーム建築・都市史研究を専門とする守田正志准教授に、この授業での狙いを聞きました。
守田正志 :建築の学びの中には、多岐に渡る分野があります。社会のあり様が急激に変化し、働き方も多様になっている時代だからこそ、できる限り多様なバリエーションを学生たちには提示したいと考えています。本授業では建築学科で教鞭を執る5つの専門分野(建築史、都市計画、建築設計、建築構造、建築構法・生産)の先生が、それぞれ1名ゲストを選びました。

今年の社会デザイン・フューチャーセッションに登壇したのは、以下のゲストの皆さまです。
・畔柳知宏(ジミクロ)
・坂田裕貴(Handi House Project)
・久山幸成(クライン ダイサム アーキテクツ)
・三渕卓(東急電鉄)
・宮田雄二郎(宮田構造設計事務所)
(五十音順、敬称略)
このうちHandi House Projectの坂田裕貴さんと、宮田構造設計事務所の宮田雄二郎さんの講義をピックアップし、その概要をご紹介しましょう。
フラットな関係性から建物を作る「Handi House Project」(坂田裕貴さん)
作るプロセスをオープンにした建築を手がける「Handi House Project」。立ち上げ当初に掲げたモットーは「妄想から打上げまで」でした。この言葉には、建物を構想する段階から打上げまでを「お金を出す人・作る人が一緒に過ごす」という思いが込められています。
Handi House Projectの坂田さんをゲストに招くことを決めたのは、建築構法計画・建築生産、コンバージョン・リノベーションなどのストック活用を専門とする江口亨准教授でした。
江口亨 :坂田さんは学生の皆さんに年齢も近く、僕らの感覚とは違うものを持っていらっしゃると思います。建物を作るとき、一般的には一番偉いのはお金を出す人で、その人が設計者と話をする。その下に下請けや孫請けの施工業者がいる上下関係が明確にあり、大きな建物を作る場合には縦の関係がどんどん強くなります。効率は良いですが、関わる人同士がフラットに話ができる関係は、そこにはありません。でもHandi House Projectさんは、この縦の関係を真横にしました。これが、これからの時代の建築ではないかと僕は感じています。

縦割りの分業を前提とした建築の現場では、誰が何を作っているのか、誰に何のお金をいくら払ったか、お施主さんが把握することはできません。一方で集合住宅のような大きな規模になると、作る側もユーザーとの距離が離れてしまい、どのように使われるかが分かりません。このような見えないこと・分からないことが、ストレスやクレームを生みやすくしているのではないか――。もともとアトリエ系の建築事務所、ゼネコンの現場監督、内装デザイン事務所に勤めていたHandi House Projectの立ち上げメンバー4人が、現場で感じたこのような問題意識からスタートしたのが、横並びのチームでプロセスを見える化する今のスタイルでした。2011年に個人事業主のユニットとして活動をスタートしたHandi House Projectは、昨年法人化し、活動の幅をさらに広げています。
彼らの特徴はフラットな関係性だけにとどまりません。設計も施工も自分たちで手がけるからこそできる、お施主さんを巻き込みながら作るワークショップ型の施工は、他にはなかなか類を見ない手法です。主には住宅や個人店舗を手がけていますが、お施主さんとの対話から、施工段階でも当初の図面をリクエストに応じて変更することや、別の可能性を提案することもあると言います。
坂田裕貴:例えばご主人が映像監督で、奥さんがアンティークショップのオーナーをやられている家を手がけたことがあります。そのときは古材や家具などが自然と集まってきたり、ご主人が自主的に部屋の扉を作られたりと、設計者が図面上で計画しても絶対に生まれ得ない、素敵な家になりました。
作るプロセスを共有しているからこそ、お施主さんのキャラクターを家に反映することができます。住んでいる人と作る人の即興性が生まれ、面白い家になる。僕らは、家はエンターテインメントだと捉えています。家づくりは『ライブ』です。記憶にも残るし、楽しい経験にもなるから、その家に子どもがいたら、子どもがものづくりに興味を持つきっかけにもなる。建築にとっても、明るい未来につながるのではないかと思っています。

木造研究を極めた建築構造技術者、宮田雄二郎さん(宮田構造設計事務所)
建物の骨組みを設計する、建築構造技術者として活躍する宮田さん。横浜国立大学の卒業生でもあり、大学を出ると構造設計事務所のプラス・ワンに就職し、数多くの構造設計を手がけました。その中で「木造」との出合いがあり、30代では東京大学で木造研究に打ち込みながら、構造設計に携わります。その後、自ら設計事務所を立ち上げ、現在は法政大学でも教鞭を執っています。
そんな宮田さんを招いたのは、二重膜構造、空間構造による構造システムの設計と解析を専門とする河端昌也准教授です。
河端昌也 :今、木造は改めて注目されていますが、宮田さんが研究を始めた15年前は全然そういう雰囲気はありませんでした。僕も話を聞いて『なぜ木造なんだろう』と思った記憶があります。そのような中で木造を学び、やがて独立されました。
建築を作るためには、構造がとても大事です。かっこいい建築を作るためには、安全に、そして法規的に作らなければなりません。そのためにはどうしたら良いかを考えるのが、構造設計です。建物がどのように壊れるか、実験による裏付けも必要で、宮田さんはそれを繰り返して今に至っておられる方です。
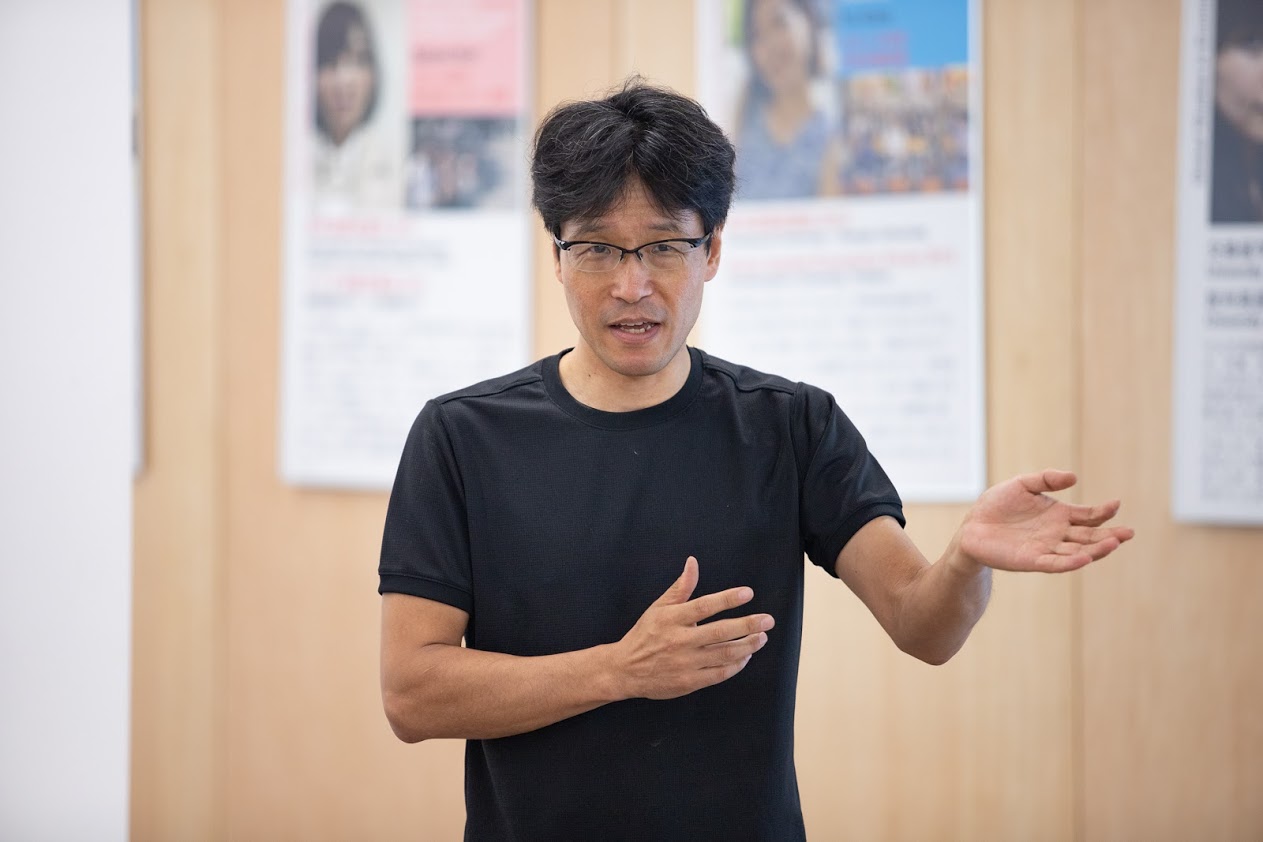
20代に所属していたプラス・ワンでは「建築家のデザインを実現するために、どのように技術的に解決するかをひたすら考えていた」宮田さん。「必ず実現できる方法はあるから、できないとは言うな」と教えられたそうです。その一方で、すべてをデザイン優先で作るのではなく、コストや安全性、施工性、社会的な責任などを天秤にかけたときの「判断」のあり方もここで学びました。つんのめってしまいそうに見える建物の実現例や、「柱をとにかく細く」という建築家の要望への対応など、紹介されたいくつもの事例から、構造設計者の苦労と技術が垣間見られました。
構造家には、構造計算だけでなく、接合方法などのディテールを一つひとつ考案する能力も問われます。木造の構造設計を担当したとき、木造のディテールについては参考になる資料がほとんど存在しないことに宮田さんは気付いたと言います。
宮田雄二郎:木造が相当難しいという現実に直面したことが、きっかけの一つになりましたね。そしてもう一つのきっかけが、コンクリートの建物を設計したときに、膨大な実験をもとに自分で書いた論文を見ながら、技術提案をしていたメーカーの担当者に出会ったことでした。
普通の構造設計者は出版された本を読み込み、そこでの知識で設計をするのですが、その担当者は自ら実験をして得た経験によって設計をしていたんです。衝撃を受けました。この二つのできごとをきっかけに、30歳でプラス・ワンを退職して、木造の研究に進むことにしました。

5名のゲストとの対話を終えて、最後に守田准教授が今年の「社会デザイン・フューチャーセッション」をこう締めくくりました。
守田 :5名のゲストのお話を聞いて、いわゆる『縦割りの社会』が崩れてきているのを感じました。第一線で活躍している人は皆、自分で手を動かし、仕事を作っていることが、共通して見えてきましたね。これからの社会で問われているのは、いかに既存の枠組みにとらわれず、新たな仕事を生み出していくかということかもしれません。
取材・文:及位友美(voids)
写真:大野隆介
社会デザイン・フューチャーセッションのゲスト
2020 年度
| 坂田裕貴 | Handi House Project(大工・設計) |
| 坂爪研一 | 乃村工藝社(建築プロデュース) |
| 宮崎晃吉 | HAGI STUDIO(建築設計、飲食店経営) |
| 宮田雄二郎 | 宮田構造設計事務所(建築の構造設計) |
| 山田貴宏 | ビオフォルム環境デザイン室(環境共生・省エネ住宅) |
| 畔柳知宏 | ジミクロ(歴史的建造物の保存とまちづくり) |
2021 年度
| 坂田裕貴 | Handi House Project(大工・設計) |
| 坂爪研一 | 乃村工藝社(建築プロデュース) |
| 宮崎晃吉 | HAGI STUDIO(建築設計、飲食店経営) |
| 宮田雄二郎 | 宮田構造設計事務所(建築の構造設計) |
| 篠原靖弘 | まち暮らし不動産(不動産、コーディネート) |
| 畔柳知宏 | ジミクロ(歴史的建造物の保存とまちづくり) |
2022 年度
| 坂田裕貴 | Handi House Project(大工・設計) |
| 坂爪研一 | 乃村工藝社(建築プロデュース) |
| 宮崎晃吉 | HAGI STUDIO(建築設計、飲食店経営) |
| 中山佳子 | 日本設計(建築設計、まちづくりブランディング) |
| 畔柳知宏 | ジミクロ(歴史的建造物の保存とまちづくり) |
| 三牧浩也 | 柏の葉アーバンデザインセンター(都市デザインマネジメント) |
2023 年度
| 杉浦悠太 | 文部科学省(建築物(学校等)の国家行政) |
| 宮崎晃吉 | HAGI STUDIO(建築設計、飲食店経営) |
| 坂田裕貴 | Handi House Project(大工・設計) |
| 枡田洋子 | 桃李舎 (建築構造設計) |
| 畔柳知宏 | ジミクロ(歴史的建造物の保存とまちづくり) |
| 坂爪研一 | 乃村工藝社(建築プロデュース) |