建築をどう学ぶ? 教育プログラムの特色と学びのプロセス

藤岡泰寛[都市科学部建築学科 准教授(建築計画)]×藤原徹平[都市科学部建築学科 准教授(建築デザイン)]
インタビュー
本学の建築学科では、建築をどのように学ぶことができるのでしょうか? その教育プログラムの特色と、学生たちの学びのプロセスを、都市科学部建築学科の藤岡泰寛准教授と藤原徹平准教授へのインタビューからひもときます。
建築学科の特色
――建築学科の大きな特色は、4つの領域「AT:建築理論」「UE:都市環境」「SE:建築工学」「AD:建築デザイン」を柱とした教育プログラムですね。学生たちは4年間でどのように建築を学んでいくのでしょうか?
藤原徹平: 1年生は教養課程を経ず、専門課程の建築学科へ入学するため、建築学科の学びの中で「教養」を学習する側面がありますね。1年次は数学や哲学、歴史や芸術などの分野を深める授業もあるので、自分の思想を組み立て直す時間になります。
建築学科を志望した1年生は、建築への興味はあるけれど、どのような研究がしたいか具体的なイメージを持つことは難しい状態にあります。そのためまずは社会の中で建築がどのような役割を担うかを考え、そのうえで建築をどう作るか、都市をどう作るかを考える教育プログラムを構成しているんです。
具体的には1~3年生の間は研究室には所属せず、座学や設計課題をとおして4つの領域を何度も行き来しながら順繰りに学んでいくことで、建築に対する考え方を身に付けます。そして自分の研究分野を3年次の終わりに決めて、4年次にようやく研究室に所属し、設計か論文の卒業研究に取り組む流れになっています。
教育の4つの領域
・AT:建築理論
・UE:都市環境
・SE:構造工学
・AD:建築デザイン
AT×UE×SE×AD――領域ごとの学びの射程
――一つひとつの領域で学ぶことと、その狙いを教えてください。
AT:建築理論
藤岡泰寛:建築理論では建築の「歴史」と「計画」を扱います。「歴史」では、建築そのものの歴史に加えて、建築をとおして見えてくる文明論や都市論なども扱いますね。昔の建築や都市を読み解くことを通じて、現代と未来の在りようを考えるという意味で、非常に重要な分野です。
一方建築の「計画」には、施設計画、住居計画といったテーマがあります。建築計画とは、構成や形式の類型「ビルディング・タイプ」を扱う分野です。現代において評価が定まっていないものを扱い、社会の変化に対応しながらビルディング・タイプの存在意義を問い直し、新しいあり方を考えていきます。歴史と計画は、相互に補完し合う関係性にありますね。
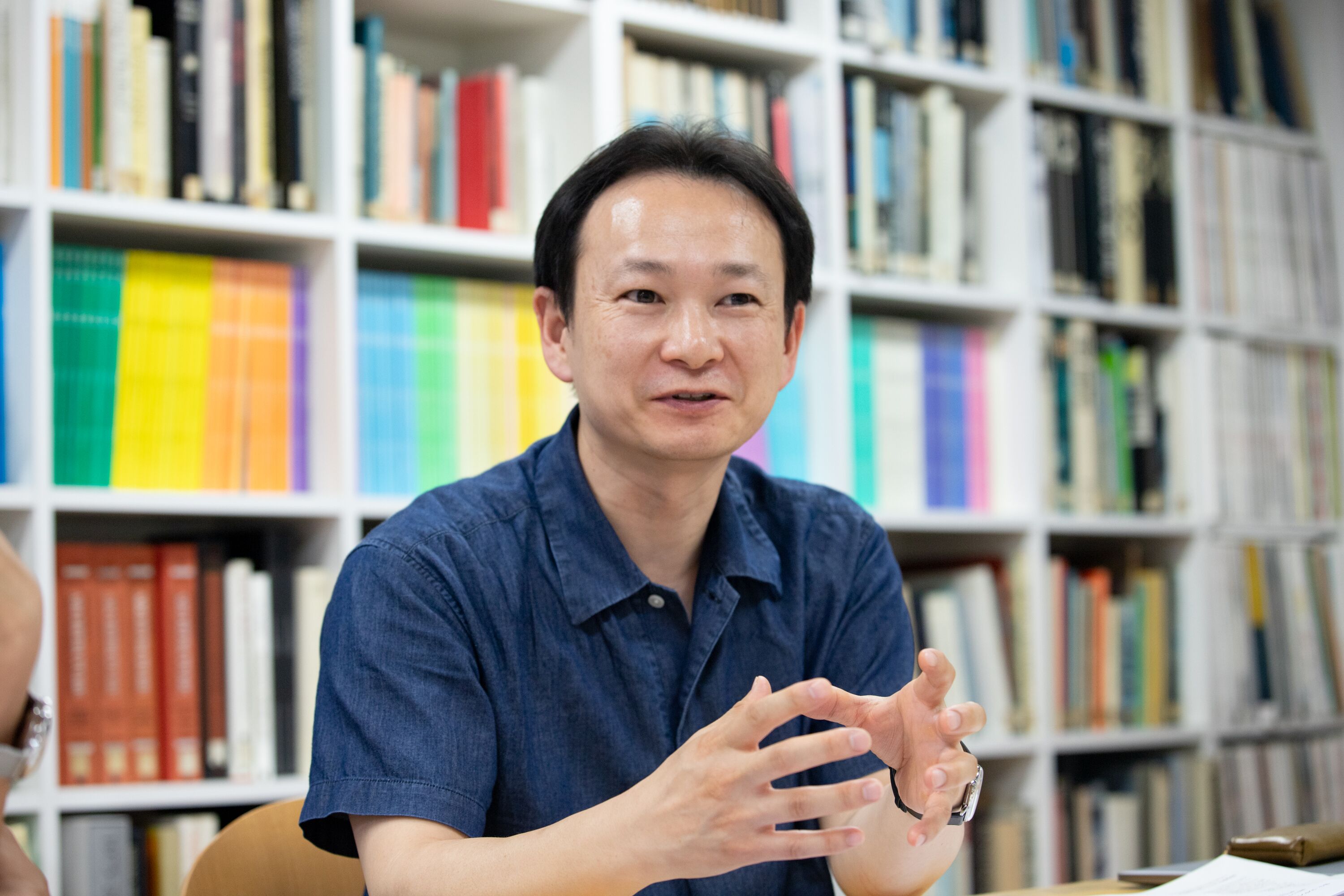
UE:都市環境
藤原:暑さ寒さや温度、音、光、熱などの環境を建築の中で考えていく分野です。本来、建築には人間にとって快適な環境を作る役割があります。建築環境工学は古くから重要な分野ですが、本学にはそれを建築単体ではなく、都市全体で考える特色があります。
建築をいかに高性能にしても、都市全体がヒートアイランド現象で暑くなっていたら意味がありません。災害に際しても同じです。建築そのものが免震構造で強くなったとしても、都市計画が機能していなければ、役割を果たすことは難しい。
建築を考えるときに都市を起点とする考え方は、AD系の大学院にあたる「Y-GSA」にも通底しています。
SE:構造工学
藤原:日本は世界有数の地震大国なので、どのように建物を作ると、どのように建物が壊れるか、どのように作ればそれがより安全なのかを、基礎から徹底して学ぶ必要があります。本学では専門的な知識を技術まで高めていく、充実した教育プログラムを組んでいます。
都市を勉強する人、建築を勉強する人、いずれにも言えることですが、建築の基本である構造を理解していないと、日本で建築を考える人になることはできません。

AD:建築デザイン
藤原:建築・都市のデザインを扱うのがADです。絵が得意な人や、デザインの造形力がある人が建築デザインに向いていると考えられがちですが、決してそんなことはありません。
理論や歴史も大事ですが、都市環境はもちろん、構造に関する知識も必要です。そのどれが欠けても、建築を考えたり作ったりする人にはなることができない。これが本学の建築教育の基本的な考え方です。逆にAT・UE・SEという3つの分野を学べば、自然と建築を作ることができるようになると我々は考えています。
4年間の学びのプロセス
――学生たちの4年間の学びは、どのようなプロセスを経て成熟していくのでしょうか?
藤原:1年次は、建築の言葉や考え方、価値観を知る授業が多く組まれています。「絵画彫塑」や「数学」、「図学」といった、建築を考えるうえで必要な基礎にじっくり取り組みます。
2年次以降は「都市や環境」といった領域や、歴史の中でも更に古い歴史へと視野を広げ、思考の領域を物理的に広げていきます。ADの設計課題もスタートします。はじめは家具、次に住宅、そして地域の拠点となる施設といった感じで、段階ごとに対象とする社会が大きくなっていきますね。
藤岡:設計課題について言えば、住宅の課題に取り組んでいる時期に、住宅に関係する講義が組まれていたり、施設系の課題の時期にはそれにつながる講義があったりします。設計課題の内容と講義が、少しずつリンクするような教育プログラムとなるように工夫しています。
藤原:学生にとっては、座学で学んだことが設計課題に使えそうだな、といった気付きがあるかもしれないし、ないかもしれません。「学び」は遅れてやってくることがあります。目の前の課題に取り組んでいるときには分からなくても、少し時間が経つと気付きがやってくるようなプログラム設計を目指しています。
さらに設計課題ではAD以外の研究分野の先生が指導に加わるシステムがあります。設計をしているときに、理論や、歴史など多様な側面のプロフェッショナルが関わるのも、学生にとっては大きいことですね。
藤岡:座学についていうと、建築学は長い歴史の中で経験則として発展してきた側面もあり、ただ内容を覚えるだけでは本当の意味で身につけることは難しい。ですが同時に設計課題を通じてトライアルアンドエラーを追体験することができれば、その理論や法則がなぜ大事にされているのかを理解することができます。座学と設計のリンクには、さまざまな狙いがありますよね。
藤原:このように3年次までは4つの領域を横断しながら、立体的だったり、時間差があったりする学びの中で、建築とは何かを理解してもらいます。そして4年次には研究室に所属して、卒業研究に取り組むというプロセスです。

卒業後の進路
――建築学科の卒業生の進路は、大学院への進学が約7割を占めていますね。
藤原:約7割なので、高いですね。大学院の修了後は、建築に関わる何らかの専門家として生きていく人が多いです。設計に携わる人はその中の2~3割で、それ以外は現場での施工や、ゼネコンや設計事務所の中で設計以外の仕事に就いたり、官公庁やハウスメーカー、研究所へ就職したりと、さまざまな進路があります。
ですが卒業生・修了生が必ずしも建築の専門家になるとは限らず、モノづくりに関わる人も居れば、編集者になる人も居ます。アメリカの大学では、建築の大学院を出ても多くの人が建築デザインに携わらない時代になっているそうです。Googleのようなソーシャルデザインをはじめ、物理的な建築にこだわらず、都市生活をどうデザインするかという視点で動いている。
建築は情報量が非常に多い分野なので、膨大な情報量を整理する力が問われます。建築の分野に進まなくても、これまで学んだことを活かして別の分野のプロフェッショナルになることもできる。建築実務につくことだけが、学生にとっての将来ではないと考えています。

対話をとおして価値観を育み、集中して学べる環境がある
――本学では「建築教育」を常にアップデートし続けているそうですね。
藤岡:横浜国大には「設計製図運営委員会」という教員の集まりがあります。横浜国大に関わる先生たちが、教授、准教授、常勤、非常勤といった立場の分け隔てなく、どの学年で、どういう設計課題を出し、どういう座学が望ましいかを全員で話し合う組織です。
藤原:「設計製図運営委員会」がスタートして約10年が経ちますが、毎年ここでの議論に基づいて課題や座学が少しずつ変わっています。うまく機能する場合もあるし、難しい場合もありますが、とにかく教育プログラムを考え、更新し続けていることが大きな特徴ですよね。とても教育熱心な学校です。
藤岡:本学の建築学科は「少人数で多様」です。1学年定員70名の少人数制で、かなりきめ細かく指導をしています。留学生もいるし、編入試験で入学する学生もいる、AO入試で入ってくる学生もいる。多様なバックグラウンドや個性をもった学生が居るので、他者と積極的にコミュニケーションを図ろうとする学生が伸びますね。他者と批評し合いながら自分なりの価値観を育てていける柔軟な学生が成長しているのではないでしょうか。
――緑に囲まれた広いキャンパスも、学生の学びを豊かなものにしています。
藤原:大らかな環境も、魅力の一つですね。学生は2年生になると、一人一台製図版が与えられますが、大学によっては全員には与えられず、朝早く登校した早いもの順に使う学校もあります。ここには競争しないと生き残れない雰囲気がないので、しっかりじっくり考えている人が、大きく伸びていきます。街と学校が物理的に離れているため、集中して没頭できる環境があるので、自ら学ぶことができる人に向いているかもしれません。

取材・文:及位友美(voids)
写真:大野隆介